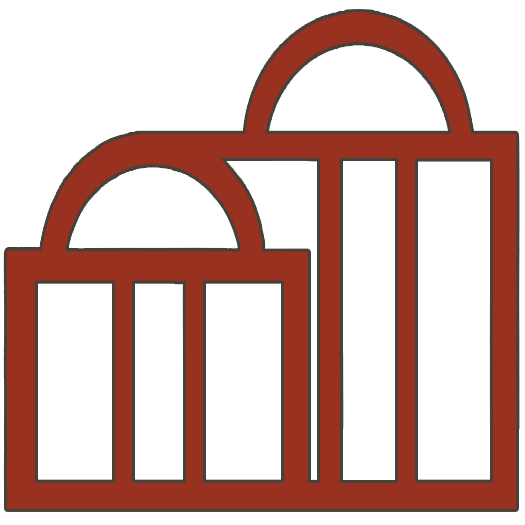アクセシビリティに関する建築基準要件に準拠するには、屋外駐車場の設計でいくつかの要素を考慮する必要があります。設計がこれらの要件にどのように準拠できるかについては、次のとおりです。
1. アクセシブルな駐車スペース: 建築基準法では、駐車場の大きさに基づいて必要なアクセシブルな駐車スペースの数を指定しています。通常、一定の割合の駐車スペースをアクセシブルに指定する必要があります。これらのスペースの具体的な寸法や標識も規制されています。たとえば、米国障害者法 (ADA) のガイドラインでは、アクセシブルな駐車スペースは最小幅 96 インチ (244 cm) と幅 60 インチ (152 cm) のアクセス通路が必要であると記載されています。
2. アクセス可能なルート: 駐車場には、駐車スペースと建物のアクセシブルな入り口を結ぶアクセシブルなルートが必要です。これらのルートは、突然のレベルの変化や障害物のないように設計され、移動機器を使用する個人のスムーズな移動経路を確保する必要があります。アクセス可能なルートで許可される最大勾配は、急な上り坂や下り坂を防ぐために、多くの場合 2 ~ 5% の勾配の間で規制されています。
3. 歩道と縁石: 駐車場から歩行者用通路への移行を提供する、適切に設計された歩道と縁石スロープが必要です。縁石スロープは、車椅子ユーザーや移動装置を持つ個人が使いやすいように、建築基準法に記載されている特定の寸法と傾斜要件に従う必要があります。
4. 標識とマーク: 明確で目に見える標識は、アクセシビリティのコンプライアンスにとって非常に重要です。駐車場の標識には、アクセシブルな駐車スペース、バンでアクセス可能なスペース、およびアクセシブルなルートの表示を含める必要があります。読みやすさのために必要な寸法とコントラスト比を遵守した、国際的なアクセス記号を使用する必要があります。さらに、アクセシブルな駐車スペースには、クロスハッチング パターンを伴うマーキングが必要な場合がよくあります。
5. 照明と視認性: 屋外駐車場、特に夜間の安全性とアクセシビリティを確保するには、適切な照明が不可欠です。建築基準法では、危険を軽減し、駐車スペース、ルート、標識などの明確な視界を確保するために必要な最小照明レベルを指定する場合があります。
6. 造園と障害物: 樹木や低木などの景観要素は、アクセス可能な駐車スペースやルートを妨げないように戦略的に配置する必要があります。このコードは通常、駐車場と隣接するエリアの両方での障害物のない通路と操作スペースの要件に対応しています。
アクセシビリティに関する建築基準要件を遵守することで、屋外駐車場が包括的であり、障害のある人が敷地内にアクセスする平等な機会が提供されます。駐車場の設計に関連する特定の条例の規定は管轄区域によって異なる場合があることに注意することが重要です。そのため、正確な情報については該当する地域の条例を参照することをお勧めします。このコードは通常、駐車場と隣接するエリアの両方での障害物のない通路と操作スペースの要件に対応しています。
アクセシビリティに関する建築基準要件を遵守することで、屋外駐車場が包括的であり、障害のある人が敷地内にアクセスする平等な機会が提供されます。駐車場の設計に関連する特定の条例の規定は管轄区域によって異なる場合があることに注意することが重要です。そのため、正確な情報については該当する地域の条例を参照することをお勧めします。このコードは通常、駐車場と隣接するエリアの両方での障害物のない通路と操作スペースの要件に対応しています。
アクセシビリティに関する建築基準要件を遵守することで、屋外駐車場が包括的であり、障害のある人が敷地内にアクセスする平等な機会が提供されます。駐車場の設計に関連する特定の条例の規定は管轄区域によって異なる場合があることに注意することが重要です。そのため、正確な情報については該当する地域の条例を参照することをお勧めします。
アクセシビリティに関する建築基準要件を遵守することで、屋外駐車場が包括的であり、障害のある人が敷地内にアクセスする平等な機会が提供されます。駐車場の設計に関連する特定の条例の規定は管轄区域によって異なる場合があることに注意することが重要です。そのため、正確な情報については該当する地域の条例を参照することをお勧めします。
アクセシビリティに関する建築基準要件を遵守することで、屋外駐車場が包括的であり、障害のある人が敷地内にアクセスする平等な機会が提供されます。駐車場の設計に関連する特定の条例の規定は管轄区域によって異なる場合があることに注意することが重要です。そのため、正確な情報については該当する地域の条例を参照することをお勧めします。
発行日: